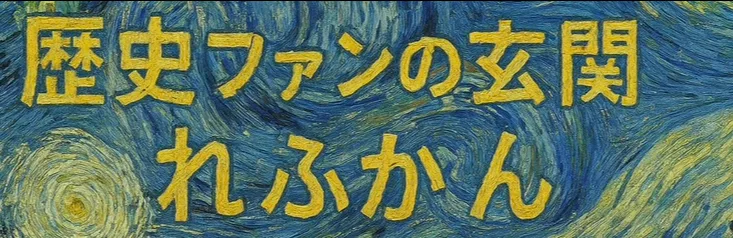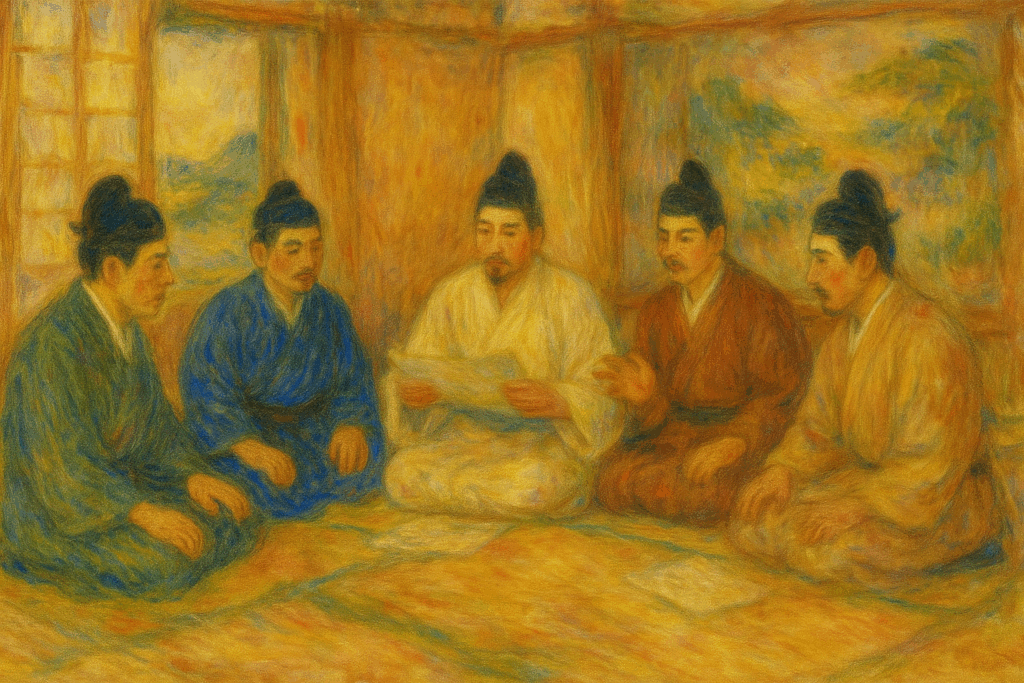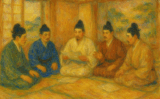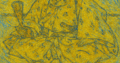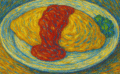慶長16年(1611年)卯月某日付
《大坂・京・江戸三都合同発行「政道かわら版」》
■石田三成、六条河原にて斬首!怒号のなか果てる
かの関ヶ原の合戦にて徳川殿に刃を交えた石田治部少輔三成殿が、先月(慶長5年10月1日)六条河原にて斬首された。戦よりおよそ半月、近江の伊吹山にて捕縛され、京に送られた三成殿は、処刑の当日、潔く首を差し出したという。
三条河原には民が押し寄せ、ある者は「義の人がなぜ斬られるのか」と嘆き、またある者は「所詮は謀略の徒、因果応報」と吐き捨てた。
市井の声:
「戦にならぬよう治めてほしかった。お上も治部少輔も、民の心など見ておらぬ」――京の商人、権兵衛(54)
■浅野長政、真壁にて静かに大往生
かつては五奉行の筆頭、そして家康公の信をも得た浅野長政殿が、常陸真壁にて病のため死去された。日付は慶長16年4月7日、齢六十五。
豊臣政権下では政を支え、徳川政権成立後も家名を守ることに成功。大きな戦には関わらず、老いてなお慎み深く、真壁の城下でも人望厚かったという。
市井の声:
「御屋形さまは、町の子らにも声をかけてくださった。武士であられるが、仏のような方だった」――真壁の農夫、庄右衛門(38)
■前田玄以、丹波にて往生す 五奉行最古の者、静寂の旅路へ
朝廷との調停役を務め、智将として名高き前田玄以殿が、慶長7年5月20日、丹波亀山にて病没された。享年六十三。
関ヶ原では西軍の文書に名を連ねながらも中立を保ち、戦後は所領を安堵された希有な存在。死に際しては一族・家臣に礼を尽くし、仏道を語ったとのこと。
市井の声:
「お上の言葉と民の橋渡しをしてくださる御方だった。ああ、世がまた騒がしくならねば良いが」――京の御用布職人、たね(61)
■長束正家、水口にて自刃!一族もろとも殉じる
関ヶ原敗北の報せを受け、長束正家殿は水口城に籠城するも、池田輝政らにより開城。慶長5年10月3日、家臣6名とともに自刃。弟・直吉殿もともに果てた。享年三十九。
正家殿は五奉行のなかでも財政を担う才を持ち、領内の民政にも定評があった。だが戦局には勝てず、潔く刃を選ばれた。
市井の声:
「主君の後を追う家臣たち、涙が出た。あの忠義が、この世にまだあるのだと……」――水口の茶屋女・おしん(29)
■増田長盛、運命の輪に翻弄され、切腹
西軍に名を連ねつつも、徳川方にも密書を送っていたとされる増田長盛殿。戦後は高野山へ追放され、のちに赦免されるも、慶長20年6月23日、大坂夏の陣の責任を問われ切腹された。享年七十一。
最期まで家名と豊臣の間で揺れた武士の末路は、まさに戦国という時代の哀しみを映す。
市井の声:
「豊臣にも、徳川にも心を砕いていたと聞く。誰かが犠牲になる世の中なら、わしら庶民には救いがない」――堺の廻船問屋、伊三郎(67)
🗞 編集部より
かつて太閤殿下を支えた五奉行、いずれもこの十年の間に命を終えたり果てたりした。その最期の姿は、武に散る者、病に伏す者、心を割かれた者、それぞれ異なるも、皆「民のための政」を志した者たちである。
彼らがいたからこそ、太閤の治世は安寧であった。いまはただ、静かに香を手向け、彼らの魂が乱世を越えて安らかであることを祈るばかりである。
(*当ブログ【歴史ファンの玄関:れふかん】は、各時代に発行された新聞記事をお届けしているかのような、他では味わえない、臨場感あふれる楽しい歴史提供を持ち味にしております)