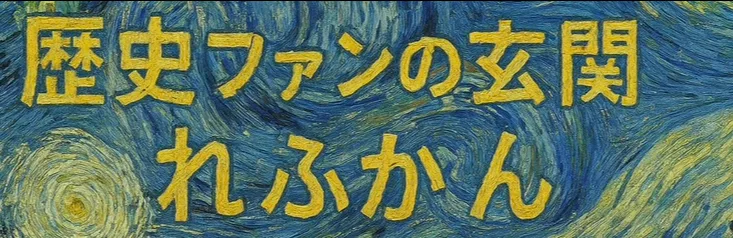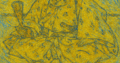桶狭間の戦い(1560年)で、仮に今川義元が織田信長に命乞い(=命を助ける代わりに金銭などを支払う)をした場合、義元が提示できた「妥当な金額」を、史実と当時の経済力に基づいて推定してみます。

📚 前提となる史実情報
| 項目 | 内容 |
| 今川義元の石高 | 約50万石から60万石(三河を除く) |
| 所領 | 駿河・遠江 |
| 金銭収入 | 年間収入約400億円(現代換算) |
| 家臣団規模 | 約25,000人(桶狭間動員) |
| 家宝・武具・仏具など | 名刀、茶器、経典など多数所持 |
🧮 金銭的な「命乞い」の相場(戦国期の事例)
実際、戦国時代には「降伏開城の謝礼」「人質の引き渡し」「敵将の助命と引き換えの金銭」などが行われていました。
よって、義元クラスの大大名が命を助けてもらうなら、120億円(今川家の年収の3割)を提示されてもおかしくありません。
💰 今川義元の「支払い能力」内訳(当時)
| 項目 | 内容 |
| 現金(銀子) | 年貢・商業収入で保有。即時動員可能金額も多い |
| 宝物 | 太刀、茶器、香炉など。価値の高いものを所持 |
| 人質 | 高家出身の親類などを差し出すことも可能 |
| 領地割譲 | 領地の一部を割譲し和睦の材料にする可能性も |
✅ 結論:今川義元が信長に命乞いの代償として払える価格(推定)
🎯 現代換算:約120億円
🧠 仮に信長が「受け入れた」場合の交渉のセリフの推測
義元「そなたの武勇、まさに天晴れ。……この命、いま少し預けられぬか」
信長「ほう。命乞いか。何を差し出す?」
義元「駿府城下の金蔵より120億円。さらに、茶器と名刀、遠江・掛川の地をそなたに」
→ 信長がこれを承諾すれば、今川家は形だけ存続する「従属大名」となり、信長は三河・遠江へ手を伸ばす足掛かりを得たかもしれません。
✅ まとめ
| 項目 | 内容 |
| 義元が払える金額の上限 | 120億円 |
| 支払い手段 | 現金、宝物、領地、人質 |
| 信長にとっての価値 | 戦利品・講和・政略の材料として十分 |
考察後の感想
実際には奇襲を受けた今川義元は命乞いをする猶予もなかったと思われますが、命乞いのチャンスがあれば、命乞いしたのかどうか気になりますね。
大金を払い命乞いに成功したとして、領地も削減され信長の家臣となった義元は、以降、信長の右腕として信長の躍進を助けることができるのでしょうか。
――信長が義元の命乞いを受け入れなかった場合は、おそらく、以降の歴史は史実と同じ展開になるので、考察する必要はなさそうですね。
(※当ブログ【歴史ファンの玄関:れふかん】は、他では味わえない、独自の考察を持ち味としています)