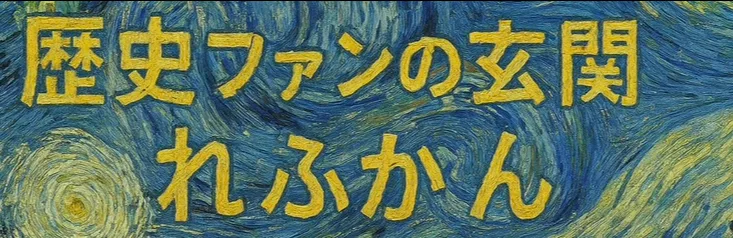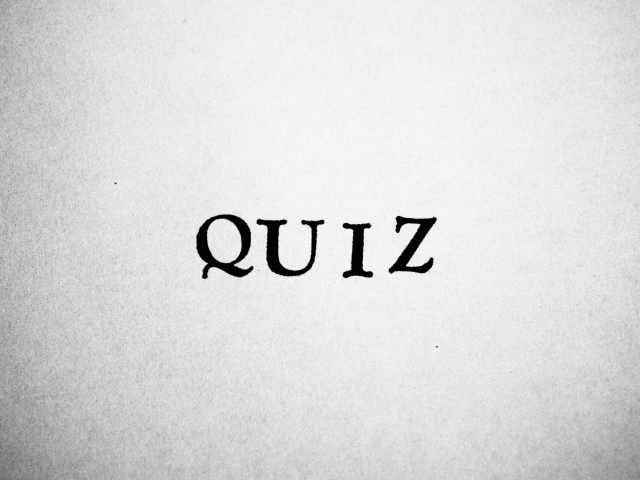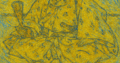最後にクイズを用意しています。
楽しんでいただけると幸いです。
*以下、紫式部と源氏物語に関する海外の反応になります。【英語のコメントをほぼGoogle翻訳で日本語化】
外国人のリアルな感想をまとめているため、翻訳されたコメントの中で紫式部や源氏物語の知識、日本の歴史に関して間違っている場合や定説でないことを主張をしている場合もあるかもしれません。予めご注意ください。
紫式部と源氏物語の海外の反応25選。
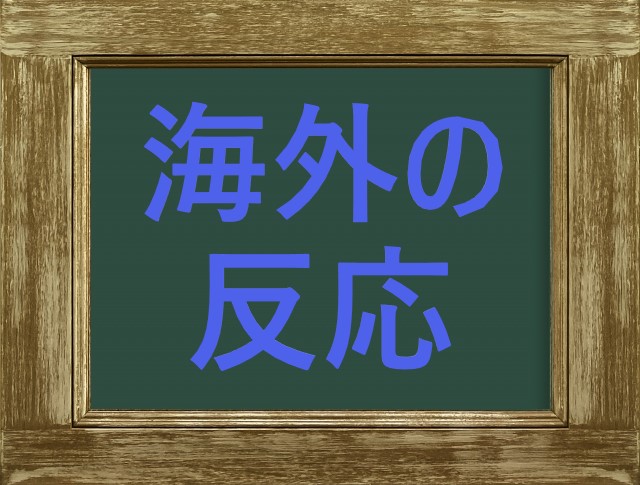
『源氏物語』は平安時代中期に成立した小説です。文献の初版は1008年。作者の紫式部にとっては生涯唯一の長編小説である。
紫式部は主人公の光源氏を通じて、愛、栄光と没落、政治的欲望と権力闘争など、平安時代の貴族社会を描いた。
光源氏のモデルは時の権力者である藤原道長です。
源氏物語の作者の紫式部は彼から求愛されましたが断りました。
その後、紫式部と藤原道長の関係は悪化し、紫式部は帰りました。
紫式部は歴史の表舞台から姿を消しました。
原因は恋愛ではなく政治にあるようです。
光源氏は女性の外見に関係なく平等に愛しました。
光源氏は母親に似た女性を心から愛していましたが、彼女があまりにも早く亡くなったので、彼はその女性の面影を探し続けました。
彼の心は永遠に帰る場所がない。それは悲劇的だ。
紫式部は藤原道長の娘の師匠だった。
しかし娘は次第に父の強引な政治行為に反発するようになり、道長は娘の謀反が紫式部の仕業であると考えて激怒し、道長は紫式部を宮中から追放した。
光源氏は孤児を家に連れかえり、育てました。母親に似た人物で、成人してから結婚しました。
紫式部が書いた世界初の女性によるちゃんとした長編小説である源氏物語はまったく期待を裏切りませんでした。
源氏物語の主人公の光源氏は、マザーコンプレックスですね。
光源氏は母親に問題を抱えているようだ。
光源氏はプレイボーイですか?
源氏物語では女性の数だけ、いろいろな女性がいるのです。
紫式部と源氏物語は学校の教科書で見たことがあります。
私は、ただこの作品を愛でています(私が読んでいる源氏物語の翻訳はアーサー・ウェイリーによるものです)。 源氏物語には素晴らしいジョークもたくさんあり、とても楽しい内容です。
私は現在、大学受験の準備をしているところです。私は入学したら専攻は日本語になります。
だから受験しなければならない試験の一つである日本文化試験の勉強をしています。
紫式部の源氏物語の分析は文学作品の概念を理解するのに非常に役立ちました。
ちょうど授業で紫式部の源氏物語の映画を見終わったところです。
私は世界で最初の女性による長編小説を読めたことを誇りに思います。
たとえば歴史書は一方的な記述であるが、
源氏物語の著者の紫式部は良くも悪くも、主人公を通じた生き方を丁寧に描いている。
源氏物語はすべてひらがなで書かれていると聞きました。 ということは、ある程度基礎的な語彙とひらがなの知識があれば、日本人でなくとも内容を何でも理解できるということでしょうか?
『源氏物語』には 10 冊の英訳現代語訳があり、初版は 1912 年で、最近では 2017 年に出版されています。恥ずかしながら、私は抄訳版と漫画版しか読んだことがありません。
紫式部が書いた源氏物語が持つ、もののあはれ、という概念は、日本の多くのアニメや漫画のキャラクターの基礎になっていると思います。
源氏物語は複雑であり、フランス語版で最もよく表現されています。
『源氏物語』はベーオウルフが書いた小説よりも古く、女性による既知の小説としては最古であるだけでなく、知られている小説の時代としても最古であるということです。
私は『源氏物語』が大好きですが、清少納言の『枕草子』も素晴らしいです。
紫式部の「源氏物語」が理想化された宮廷社会であるとすれば、清少納言の「枕草子」は現実の生活と、物事が常に自分の思い通りに機能するとは限らないことについての物語です。
紫式部の興味深い点は、彼女が貴族階級に生まれたにもかかわらず、藤原家の非常に強力な本家・分家の出身ではないということです。 しかし、権力者である藤原道長は、おそらく紫式部が有名な小説家だったため、娘である皇后に出席するために彼女を宮廷に連れて行ったと私は思います。
紫式部は、彼女の本当の名前さえ不明です。 紫式部は学者によって割り当てられ、学者はこの本の主要な女性登場人物の名前「紫」と著者の父親の典礼局での役職「式部」を使用して彼女を特定しました。
外国人と紫式部と源氏物語(海外の反応から推測)
・源氏物語を日本関連の授業で習った外国人が紫式部について知るパターンが多い。
・紫式部本人よりも、紫式部の書いた『源氏物語』の方が外国人たちに興味を持たれており、知名度が高い傾向がある。
・源氏物語が世界最古の女性による長編小説であると主張し、その知識を自慢気に披露する外国人が幾人もいる。